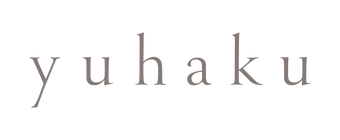「トライアル&エラーの積み重ねが、これからの表現を創る」
Rhizomatiks主宰 真鍋大度氏

日本を代表するクリエイターをゲストに招き、独自の仕事術を伺う本連載。第十二回は日本を代表するトップクリエイター、真鍋大度氏。インタラクティブアートを通じた、人とテクノロジーの新たなコミュニケーションを提案し、テクノポップユニットPerfumeのライブ演出の技術サポートやリオ2016大会閉会式東京2020のフラッグハンドオーバーセレモニーでのAR映像演出など、様々なクリエイションで見る人を驚かせ、楽しませてきた。現在までに至る道のりと、これからのメディアアートに対する想いを聞いた。
Index
1. Work 2. Interview ・数学好きの秀才が、HIPHOPの虜に ・大学時代に出会った1冊の本に感化される ・フックとなる“点”を作り続けることの大切さ ・常に研究開発を行い、アイデアを蓄積する ・コロナ禍で見えた、加速するメディアアートの未来 3. Column 日々を彩るプロフェッショナルの愛用品 4. Goods 真鍋大度氏が選ぶyuhakuのアイテム 5. Profile
Work
Daito Manabe "electric stimulus to face -test3"
Squarepusher “Terminal Slam”(MV)
KAZU “Come Behind Me, So Good!“(MV)
ELEVENPLAY x Rhizomatiks “S . P . A . C . E .”(2020)
Daito Manabe "electric stimulus to face -test3"
Squarepusher “Terminal Slam”(MV)
KAZU “Come Behind Me, So Good!“(MV)
ELEVENPLAY x Rhizomatiks “S . P . A . C . E .”(2020)
interview
「トライアル&エラーの積み重ねが、これからの表現を創る」
数学好きの秀才が、HIPHOPの虜に
技術と表現の新しい可能性を探求し、最先端のテクノロジーを用いたアート作品を次々と発表するライゾマティクス。その創設者の1人であり、中心人物として活躍する真鍋さんはこれまで、Perfume、ビョーク、サカナクション、OK Goなど、数々のアーティストとのコラボレーションで話題を提供してきた。AR(拡張現実)を駆使しして世界中を沸かせてみせたリオ2016大会閉会式東京2020のフラッグハンドオーバーセレモニーも記憶に新しい。そんな真鍋さんがテクノロジーに興味を持ったきっかけは、小学生の頃にまで遡る。 「僕ら世代の人には多いと思いますが、当時のPC8801やMSXというパソコンを親が買って、それで子供も興味を持つというパターン。なので珍しい感じではないと思いますが、とにかくそれで、当時流行っていたベーシックというプログラミング言語を学ぶようになったのが小学生のとき。ファミコンを買って貰えなかったので、自分で簡単なゲームを作ったりして遊んでいました」

論理的な思考が鍛えられたからか、中学生になると数学の才能が開花。模擬試験では、なんと偏差値90以上、中学三年生の時には大学センター試験の数学で満点を叩き出すほどの実力だったという。しかし、生まれ育った場所は東京の恵比寿。中学3年生になる頃にはスケートボードやDJといったカルチャーにのめり込むようになっていく。 「たまたま同時期に恵比寿ガーデンプレイスが建ったことで家にテレビの電波が入らなくなり、ケーブルテレビが提供され観られるようになったんです。そうしたら音楽専門チャンネルのMTVにハマってしまって。そこからはヒップホップにどっぷり。バトルDJに憧れて、高校生の頃には大会に参加したりビートメイクをしたり、それが大学に入ってからは加速しました。」 どちらかと言えば、職人芸を突き詰めたいタイプで、スクラッチの練習には余念が無かった真鍋青年。さらに大学に入ってからは音ネタを作るする際にも既存の音楽ソフトだけでは飽き足らず、自分でツールを開発していたというから驚きだ。 「そこでのプログラミングの知識が生きてくるとは、世の中どうなるか分からないですよね(笑)」
大学時代に出会った1冊の本に感化される
自分が作った音楽ツールで、自分の音楽を作る。大学生にして独自の表現を志す真鍋さんだったが、“いつもニッチな方向にいってしまう”と当時を振り返る。 「その頃から人気商売に対して斜に構えているところがあり、お客さんウケを狙うみたいなことが性に合わなくなってしまって。そんな風だからDJやビートメイカーとして人気が出るわけもなく、徐々に音楽は趣味で続けていこうというスタンスになっていきました」 進学したのは、得意だった数学と英語(小学生時代にアメリカで過ごした時期がある)で受験できるという理由で東京理科大学の数学科。そこで現在の真鍋さんに繋がる重要な1冊と出会う。ギリシア系フランス人の作曲家、ヤニス・クセナキスが1971年に書いた『音楽と建築』だ。

「1番感銘を受けたのは、僕が当時勉強していた代数学や確率論を使った作曲方法を、その時代にすでにやっている人が実在したということでした。数学は得意で、音楽も好きだから自分にも出来ると思ったのですが、当時は機材や環境がなかなか揃わず、思い描いていたことが実現出来ませんでした。その後システムエンジニアとして就職し、次にIT系の会社に転職していく中で、“プログラミングと作曲のスキルを組み合わせた表現を極めよう”と思うようになったのは、この本があったお陰です」 しかし、同時にぶち当たったのが、表現することの難しさ。そこで真鍋さんは、プログラミングで表現をするとはどういうことか、それを学ぶために岐阜県にある国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)に入学することになる。
フックとなる“点”を作り続けることの大切さ
「IAMASで学んだのは、『表現は自由でいい』ということでした。当時の僕は制約がある中で何かを考えるのは得意でしたが、常識に囚われるなと言われると難しかった。先生のレビューが厳しい環境の中、ひたすら作品研究と制作を繰り返す日々。同級生の年齢も人種も職業もバラバラで、カルチャーショックを受けながらもコンセプトや文脈の大切さを学ぶうちに、少しずつ意識が変わっていきました。とはいえ、作品で食べていけるようになるとは思っていなかったです」 卒業後は、東京藝術大学で講師などの仕事をしながら、自分の作品制作や新しい表現を生み出すための実験に熱中する日々。ライゾマティクスを立ち上げたのもこの頃だ。創業メンバーでもある友人たちと借りたシェアオフィスで寝泊まりしながら、文字通り身を削るような時期もあった。その後、作曲とプログラミングを武器に、舞台芸術やインタラクティブアートの現場へと、少しずつ活躍の幅を広げていく。 2008年、そんな真鍋さんに人生最大のターニングポイントが訪れる。実験の記録としてYouTubeにアップしていた動画「electric stimulus to face」(顔面に筋電センサーと低周波刺激装置を繋ぎ、音の電気信号で顔を動かす実験的な内容)が世界的に“バズった”のである。

「海外のギーク系メディアが動画を取り上げてくれたのをきっかけに世界中に拡散され、突然何千件という問い合わせが舞い込みました。中でも印象的だったのが、アルスエレクトロニカというメディアアートの祭典のディレクターから招待を受けて、いきなりそのオープニングイベントのトリを任されたこと。動画をきっかけに、かなり仕事の幅が広がりました」 真鍋さんにとっては青天の霹靂。しかし、チャンスをものに出来たのは、自分の表現を模索するために学ぶことを止めず、フックとなる“点”を作り続けてきたからこそだった。 「自分では運が良かっただけだと思っていますが、一方でアルスエレクトロニカのディレクターから『あの動画一本だけだったら招待していなかった』と言われました。実は有名になった動画はYouTubeにアップしていた何十本という実験動画の内のひとつで、他にもたくさん再生されていない動画があるんです。それがあったからオファーをいただいたのだと思います」


常に研究開発を行い、アイデアを蓄積する
そこからの真鍋さんの活躍は冒頭でご紹介した通りだが、今も昔も、クリエイションのプロセスは大きくは変わっていない。とにかく実験を重ね、模索し続けること。それに加えて、歴史的な背景などのリサーチにもかなりの時間を割いているという。 「アートにおいては、新しいものを発明することだけでなく、今までの歴史や文脈の中で自分の作品がどこに位置づけられるのか、ということが大切。例えばライゾマがイレブンプレイとやっているパフォーマンス作品は20世紀前半のバウハウスの芸術家、オスカー・シュレンマーがやっていた舞台芸術の現代版みたいなイメージなのですが、そういうことを知った上でやるのと、知らずに『自分がこんなに面白いことを思いついた!』とやるのとでは、作品の意味も変わってきますよね。なんというか、ヒップホップで元ネタのジャズを探すのに近い感覚なんですよ」 重要なのは、そうしたリサーチを含めた日々の研究開発を怠らず、YouTubeに実験動画をアップし続けてきたのと同じように、アイデアを蓄積していくことだ。 「自分の作品であれば納得いくまで突き詰められますが、広告やアーティストとのコラボレーションは製作期間が限られているので、依頼が来てから考え始めるのでは遅い。しかし、案件の内容に合わせて相応しいアイデアをチョイスする形であれば、スピーディかつ最大限の効果を発揮できます。だからライゾマティクスではクライアントベースの仕事とは別軸で、常に研究開発を行っているんです」
コロナ禍で見えた、加速するメディアアートの未来
「例えばバーチャルミュージアムやクリプトアートって、今までメディアアーティストたちは面白いと思って取り組んできましたけれど、現代美術、現代アートの人々にとっては別になくても良かったですよね。でもコロナ禍になったことで、もはやそれがないと作品を展示できないような状況になってしまいました。こうなってくるとテクノロジーの力を使わないと未来が切り開けないどころか、現状に対応出来ないのは明らかです」
Column
日々を彩るプロフェッショナルの愛用品
プロフェッショナルたちが普段持ち歩いている必需品や仕事道具を見せていただきながら、モノに対するこだわりを紐解く。
「基本的には裏方仕事なので、服や小物は自然と黒を選ぶことが多いですね」と真鍋さん。特に光を使った演出などを行う場合、白やカラフルな色は、時として作品の邪魔になってしまうことも。慣習として黒を選ぶ人が多いのは確かだ。しかし少し視野を広げてみると愛用品は実に多彩だ。

AppleのAirPods Pro
「音楽を聴くヘッドホンは別にあるので、これはラジオやオンライン会議をする時に使用しています」というのがAirPods Pro。ノイズキャンセリング機能付きなので、もともと世界中を飛び回る真鍋さんには欠かせないツールの一つだ。

VICTORINOXの十徳 「家にいるときにはもちろん、現場でダンボールを開ける時など、日常の中で意外とあると役に立つんです。直近はコロナ禍で飛行機に乗ることもないので、自分用として愛用しています」

AppleのiPad Pro 様々なプロフェッショナルたちを支えるiPad Pro。中でも真鍋さんは画面サイズの大きな12インチを愛用している。「アイデアをスケッチするとき、動画を確認するとき、さらに舞台装置などのコントローラーとしても使える。何でもできますね」という通り、様々なシーンで活用している。

audio-technicaのATH-AWAS ハウジングに高品質なアサダ桜を使い、クリアな音場を再現しながら、温かみのある音色を奏でるロングセラーのヘッドホン。「父親がジャズベーシストであることもあり、昔からベースを中心に音楽を聴く癖があるんです。だからベースの音が綺麗に聞こえるコレを選びました」

Oura Ring 指輪型の体調管理ガジェットとして話題のオーラリングは、真鍋さんらしく黒をチョイス。「Apple Watchでも睡眠や心拍数の変化を記録できるのですが、充電するのを忘れてバッテリーを切らしてしまうこともあるので……。これは5日間くらいは付けっぱなしでも大丈夫ですし、記録できる数値も正確です」

AppleのApple Watch 「デザインだけでなく、自分で好きな機能を開発できる時計として使っています」というように、自ら開発したアプリをインストールすることで、Apple Watchをより便利に使えるようにカスタムしているという。なんとも真鍋さんらしい使い方だ。

sacai×POLAROIDのSX-70 1972年に発売され、アンディ・ウォーホルが愛用していたことでも知られるポラロイド社の名機、SX-70をオーバーホールし、カラフルなベロアや塗装でサカイらしいアレンジを加えたコラボモデル。「sacaiもPOLAROIDも好きだったので迷わず買いました」

Ssupremeのディレクターズチェア 椅子が快適すぎるとずっと仕事をしてしまうという理由から、あえて長時間座るには心許ない椅子を仕事場のデスクで使用しているという真鍋さん。「本当は丸椅子でも良いくらいなんですけどね(笑)。Supremeは高校生のころから好きで着ていますが、ミニマルなデザインが多く、古くならないところが良いですね」
Goods
真鍋大度氏が選ぶyuhakuのアイテム氏が選ぶyuhakuのアイテム


今回、真鍋さんに選んでいただき贈らせてもらったのが、牛革にインクジェットプリントを使用し、職人による手染めを忠実に再現した撥水レザーのポーチ&エコバッグ(※販売終了)と、手染めによる美しい色彩のグラデーションを施したクロコダイル革を採用したApple Watch用ベルト(YFA500/501)だ。 「普段色のあるものを身に着けない自分にとって、グラデーションは新鮮。エコバッグ用のポーチなのですが、丁度良いサイズだったので、普段は領収書入れとして使っています。ベルトは、黒いApple Watchにとてもマッチしますし、今まで使っていた純正のラバー系のものと比べて、綺麗に光を反射してくれるところが素敵だと思います」
Profile
真鍋大度
東京を拠点に活動するアーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマ、DJ。2006年Rhizomatiks 設立、2015年よりRhizomatiksの中でもR&D的要素の強いプロジェクトを行うRhizomatiks Researchを石橋素氏と共同主宰。身近な現象や素材を異なる目線で捉え直し、組み合わせることで作品を制作。高解像度、高臨場感といったリッチな表現を目指すのでなく、注意深く観察することにより発見できる現象、身体、プログラミング、コンピュータそのものが持つ本質的な面白さや、アナログとデジタル、リアルとバーチャルの関係性、境界線に着目し、デザイン、アート、エンターテイメントの領域で活動している。